CVC・事業会社の進化に向けたM&A活用:案件事例と実体験から学ぶ成功のヒント | Tokyo Venture Capital Hubでの講演
2025.10.28
2025年10月14日(火)、当社マネージングディレクターの久保田朋彦が、Tokyo Venture Capital Hub会員企業向けイベントにて、「CVC・事業会社におけるM&A戦略と実務の最前線」をテーマに登壇いたしました。
これまで、コーポレート・ベンチャー・キャピタル(CVC)を設立してきた事業会社が、次の成長に向けて投資方針の見直しを進めており、事業シナジーを本格的に追求するために、100%買収を選択肢とする動きが加速しています。
久保田が自身の豊富なアドバイザー経験を踏まえ、CVC・事業会社が今後果たすべき役割について実践的な提言を行い、当日は活発な議論が展開されました。

サマリー
案件に学ぶ:イグジット戦略はIPOからM&Aへ ─決断力とコミットメントがカギ
- 近年、スタートアップの買収に関心を示すファンドや事業会社が多くなっています。また、投資家(VC)や対象会社においても、以前はイグジットといえばIPOが主流でしたが、現在ではM&Aも重要な選択肢として検討されるようになりました。
- 実際、当社がアドバイスした案件でも、当初はIPOを目指していたクライアントが、最終的にM&Aを選択するケースが増加しています。
- 当社の強みは、国内外のネットワークを活用し、日本だけでなく海外の事業会社やファンドを買い手として成約に導ける点です。特に、今後は小規模IPOから中・大型IPOへと市場環境がシフトする中で、同時に増加傾向にある国内外のグロース型ファンドを活用し、VCエグジットと上場までの期間を繋ぐ「上場前ブリッジ型バイアウト」が新たな選択肢として大きな可能性を秘めていると考えています。
- 投資した資金の回収手段は、IPOかM&Aに限られます。そのため、投資前から創業者やマネジメントと出口戦略 を検討しておくことが重要です。たとえば、「このケースではIPO、別のケースではM&A」といったシナリオを、投資前または投資時に共有しておくと効果的です。
- これまでの日本では、IPOが主な成功シナリオとされてきました。しかし最近では、一定の条件下ではM&Aのほうが、売り手・買い手双方にとって望ましい結果となるケースが増えています。
- 証券市場からのプレッシャーやガバナンス強化、アクティビストによる影響もあり、上場後に株主と丁寧に対話するにはコストがかかります。そのため、むしろ一人株主と向き合いながら会社を成長させる方が望ましいと考える企業も増えてきました。
買手のバリュエーションアプローチ、大切なのは事業計画と確実な業績達成
- クリーンイグジットを実現するには、事業計画の精度が不可欠です。月次の売上や利益が計画通りに推移しているかは、事業計画の信頼性を測るうえで非常に重要な指標となります。
- 事業会社は事業計画をベースとしてディスカウント・キャッシュ・フロー(DCF)に基づいて価値を算定しますが、その際シナジーバリューを見込むことがあります。シナジーバリューは、自社で手がけられない領域に外部の知見やリソースを取り込むことで生まれます。シナジーを最大化できる事業会社の買い手は、ファンドよりも高いバリューを提示できる可能性があります。
- 一方、ファンドは、拠出するエクイティに対して最終イグジット時のMOIC(Multiple on Invested Capital)やIRRを算出するエクイティーリターン分析を行いますが、同分析の基盤となるのも、精度の高い事業計画です。
成長へのコミットメントが成功を決める ─買収形態と関係性の本質
- 本来、事業会社がスタートアップへの資本参加を検討する場合であっても、マイノリティ出資ではなく 100%買収 の形で関与することが望ましいです。マイノリティ出資では、両社のコミットメントが弱くなりやすく、成長支援の効果も限定的になりがちです。
- 100%買収を行うと、買い手に強いコミットメントが生まれ、本気で成長支援に取り組むようになります。一方で、マイノリティ出資では当事者意識や推進力が弱まりやすく、十分なバリューアップにつながらないことがあります。たとえば、事業会社が「この事業部が本件買収の投資責任を持つ」となると、リスクを背負う責任感から、真剣に価値向上に取り組むようになります。買い手と売り手の思いが一致したときに、初めて投資の価値が生まれるのです。成長へのコミットメントこそが成功の鍵となります。
- 事業会社が買い手となる場合、買収後に本体へ統合するか、独立した“出島”として残すかは、しばしば議論となるポイントです。いずれの形を採るにせよ、双方のリスペクトが前提にあれば大きな問題はありません。ただし、スタートアップの場合、上下関係が過度に強調されるとマネジメントの反発を招く可能性があります。加えて、被買収側のモチベーションを維持・向上させる工夫が重要です。
成功を導く視点と、アドバイザーの果たすべき役割
- 企業の成功は、評価するタイミングや時間軸によって大きく変わるといえます。たとえば、過去に積極的な海外展開で大きな成果を上げた企業であっても、現在では事業の見直しや撤退を進めているケースがあります。このような変化は、企業の成長が常に一定ではなく、戦略、市場環境、外部要因、社内事情など多様な要素に左右されることを示しています。
- そのため、成長は永続するものではないという前提に立ち、次なる成長機会をいかに見出すかが経営における重要な課題となります。変化を前向きに捉え、柔軟に対応する姿勢と、一定のリスクを取る覚悟が、持続的な企業価値の創出につながります。
- 当社は、買収された側としての実体験を持つ数少ないM&Aアドバイザーです。そのため、売り手の立場や心理を深く理解したうえで、適切なアドバイスが可能です。売り手のモチベーションを高め、前向きな姿勢を引き出すことは、円滑なプロセスのために欠かせません。アドバイザーとしての真価は、信頼関係の構築とディールを完遂へ導く力にあり、当社はその両面において、実務経験に基づく支援を提供しています。
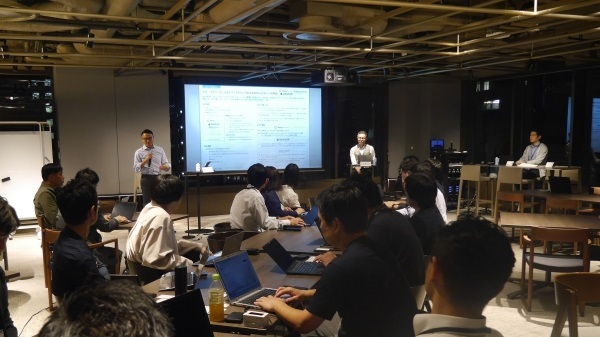
記事監修
この記事を監修している弊社担当者です。


