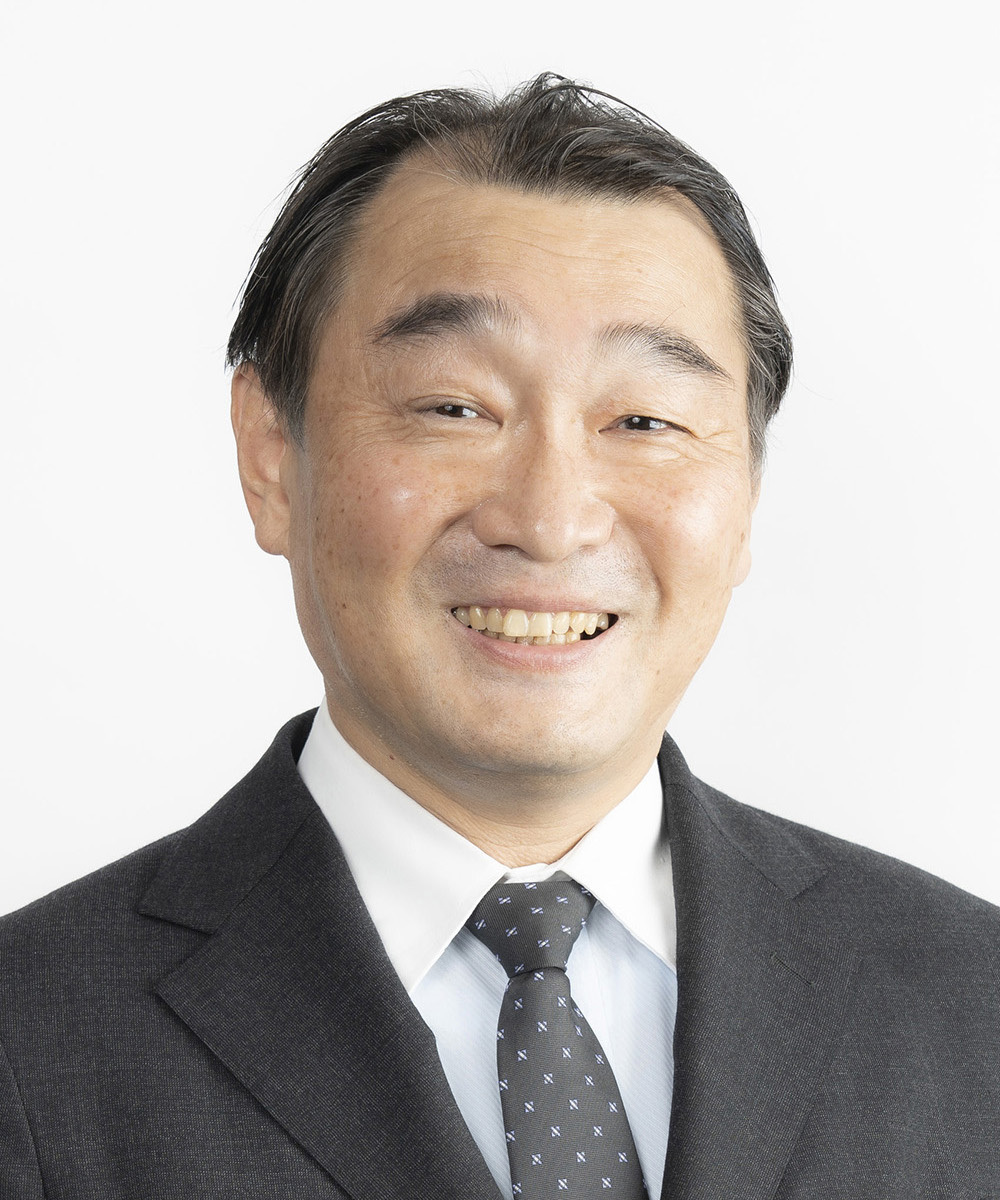The Takeaway |海外の不採算・ターンアラウンド事業の売却について住吉克洋とのQ&A
日本企業による海外(特に、米国・欧州)の不採算・ターンアラウンド中の事業・子会社の売却が活発化しており、今後も増加が見込まれています。
今回はこの傾向について、当社インダストリアルチームの住吉克洋が、直近2-3年における特に製造業を中心とした10案件以上に対する助言や執行における、自身の経験をふまえて解説いたします。
ー 昨今、特に、海外の不採算事業のM&Aを通じた売却撤退が増えてきているのはなぜでしょうか?
特に日本の製造業の欧米における製造・販売拠点の戦略的位置づけや、サプライチェーンの見直し、その競争力が大きく変化したためです。コロナ禍、ウクライナ戦争以来の世界的なインフレやエネルギー価格の上昇、保護貿易主義の台頭、直近のトランプの関税政策による世界経済の混乱といった外部環境の変化により、海外事業の採算が悪化し、清算・撤退を検討する子会社・事業が増えてきている背景があります。
一方で、欧米には不採算事業のみならず、ESGやEV化の流れの中で、上場企業(パブリックキャピタル)が継続保有し続ける意味を、一般株主に説明することが難しくなりつつある事業(ICE関連事業、反ESG事業等)であっても、投資が可能である金融投資家(プライベートキャピタル)が幅広く存在します。彼らの中には、Exit(転売)を必要とせず、投資後の買収企業のキャッシュフローにて投下資金を回収する投資家も存在します。日本の製造業とは全く異なる視点から対象事業を分析し、独自の基準で投資行動をとる、このような投資家が、買手候補として日本企業から注目度が高まっています。
結果として、持参金付きやアーンアウト等のアップサイドを残した形も含め、さまざまなストラクチャーのM&Aによる売却が増えつつあります。
ー 清算による撤退ではなく、M&Aによる売却をマネジメントが選択するのはなぜでしょうか?
不採算事業のM&A売却による撤退を行う決定は、①金銭的な負担 ②時間 ③レピュテーションの観点から、清算の場合と比較検討されることが多いです。
清算を行う際の金銭的負担に関しては、清算時の負債(退職年金関連、環境関連やその他の簿外債務等を含む)、従業員の雇用解除に伴う費用、取引先との供給義務等による一定期間の赤字操業、他社への調達供給の切り替え、完全に撤退するまでの操業コスト、清算のために費やすマネジメント労力等、莫大なコストがかかる可能性があります。また、時間に関しても、清算が完了するまでは、従業員や取引先との関係や原状回復義務等にもよりますが、通常、2-3年ほどはかかります。また、会社・事業を清算したというマネジメントのレピュテーションにマイナス影響がでることもあります。
一方で、M&Aによる売却の場合は、清算時と比較して、金銭的負担が大幅に軽減されることが多いです。対象事業の人気度や売却プロセスによっては、持参金付きの売却を前提としつつも、持参金なし、あるいは売却代金がプラスになることもあります。加えて、新たな投資家によるリストラが成功した際のアップサイドを享受できる形で譲渡できる事例もあります(ベンダーローンの返済、アーンアウト等)。売却のプロセスを開始してから、一年未満での売却が可能であり、時間的にも清算と比較して大幅に短縮が期待されます。もちろん、通常のM&Aの取引と変わらず公表されるので、会社を清算したというマイナスのレピュテーションも立ちません。M&Aによる売却は、極めて有効な選択肢となり得ます。
ー 不採算事業のM&Aによる売却を行う際の留意点はなんでしょうか?
対象事業の将来見通しや事業計画について、投資家ごとに、売り手との目線の高さが異なることは多いです。そのため、デューデリジェンスの途中で、価格を含む諸条件が当初の前提と違ったという理由で買手候補がいなくなったり、買収候補から想定外の条件が出てきて、売却をストップせざるを得なくなる可能性を考慮すべきです。売却プロセス期間中も対象事業の赤字は継続していることが多いため、直接、清算プロセスに入る場合に比して、余分な時間と費用をかけてしまうことになります。
また、新たな投資家の下で譲渡事業・会社の経営が立ち行かなくなるリスクをも勘案したうえでの適切な売却先の選定の必要性や、経営が失敗した際に、売却以前の経営の是非を問われる等の法的(クローバックリスク等)・経済的・社会的・道義的リスクを十分マネージすることも、とても重要になってきます。
ー 具体的には、買収候補者と売り手の目線を合わせつつ売却プロセスを進めるためには、どのようにしたらよいのでしょうか?
売り手は情報漏洩に配慮し、できるだけ多くの適切な買収候補者に声をかけつつも、プレマーケティングや、ファイヤーサイドチャット、オークションにおいては1次・2次ビッドに加えて、1.5次ビッド等を行うことで、常に、買収候補者の対象会社への興味を確認することが重要です。興味のあるアセットの範囲のヒアリング、バリュエーション、対象会社のマネジメントや従業員に対する考え方、ベンダーデューデリジェンスの必要性、表明保証保険の活用ニーズや独禁関連の届け出等の売却プロセス設計に必要な項目の確認を行い、より効率的かつ柔軟に、売り手の利益の最大化を図るべく、売却プロセスをすすめることが重要です。
ー M&Aによる売却の意思決定を行う際に、特に重要な条件の一つである価格は、不採算事業の場合どう考えたらよいのでしょうか?
不採算事業の買手候補となる金融投資家は、「①売却時における債務(簿外債務、偶発債務も含む)」、「②対象事業が黒字化するまで、必要な運転資金(通常は、2-3年で黒字化する前提)」を価格のスタートライン(最低価格)として念頭に置き、「③リストラ成功時の利益水準」をみながら、最終価格を決定してくるということが多いと思います。①+②の合計額を持参金としつつ、③をどれだけ上乗せするかが投資家の提示価格となるようです。
したがって、売り手側としては、清算を行う場合のコストと、M&A売却時の最低価格と考えられる①と②の合計額を比較して、有意な差がある場合に、M&A売却による撤退を決定することになります。
我々が関わった事例では、清算によるコストが最低でも100-200億円は下らない一方で、M&A売却による最低価格(①+②)が50-80億円ぐらいと試算された案件で、最終的には、持参金が十数億円あるいは持参金なし(+アーンアウト等)といった、売却価格がプラスの場合もある好条件で売却ができた事例もいくつかあります。M&Aによる売却が金銭面でかなり優位となる結果が散見されます。
ー 適切な買収候補者とはどのような投資家でしょうか?
売却プロセスが進むにつれて、リストラ案件の場合は投資家間で将来の見立てに乖離があることを理由に、交渉の終盤に当初の条件と大幅に内容の異なる提案や、思いもよらない要求をしてくる買収候補者がいます。
また、対象事業売却後、新たな投資家の下で、一定期間中に対象会社の経営が悪化し、倒産等に見舞われた際に、過去の株主・経営者にさかのぼってその経営責任を問うクローバックリスクのような制度が国によっては存在します。
新たな投資家との売買契約の内容によって、このような法的・経済的なリスクを軽減することはもちろんのこと、レピュテーション等の社会的・道義的リスクも売り手は考慮しながら、買収候補者の属性なり過去の投資行動に基づく信用力を慎重に検討する必要があります。
戦略的投資家の場合は、金融投資家と比べて、開示情報の制約や独禁法上のクリアランス等も含め買収完了までの時間がかかることがあります。一方で、シナジーによる価格の切り上げ期待ができます。過去においては、金融投資家のみを招聘した場合や、戦略的投資家も同時に招聘した事例もあり、案件に応じた適切な買収候補者を選定することはとても重要なポイントとなります。
ー このような不採算事業のM&A売却を行う際の、フーリハン・ローキーの役割とはなんでしょうか?
当社は、グローバルで2,000社近くの様々な金融投資家とお付き合いがあり、それぞれの属性、投資スタイル、投資基準や方針、交渉スタイル、信用度、投資実績等を熟知しています。売却対象となる事業の特性や特徴、売り手企業のニーズを勘案しながら、当社のネットワークをフル活用して、適切な買収候補者の紹介、その意向を確認しつつ、売り手にとっての売却の妥当性や確実性を担保し、売却プロセスの設計や案件の執行、交渉のお手伝いをさせていただいております。
リストラが待ったなしに必要とされる、確実性と時間が極めて重要な不採算事業のM&Aの売却において、当社の多数の経験値を活用しながら、効率的でかつリスクを把握・管理したうえでの売却をサポートいたします。
記事監修
この記事を監修している弊社担当者です。