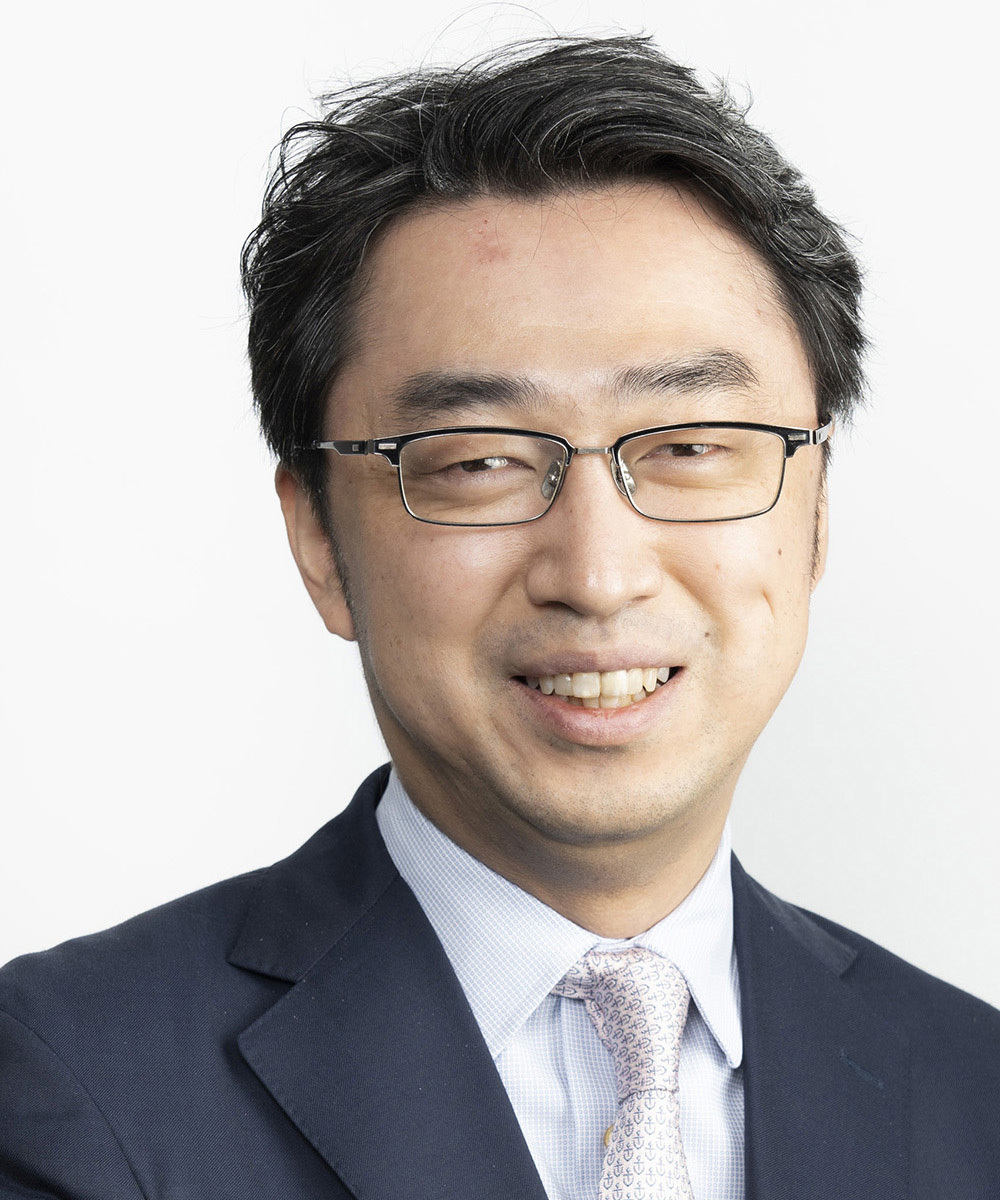The Takeaway |トランザクション・ボーナス ~事業売却のための不平等な投資~ 山崎洋一とのQ&A
トランザクション・ボーナスとは、事業売却が成約(クローズ)した場合に限り、売却対象事業の経営陣に払われる特別ボーナスです。欧米ではかなり普及しており、過去に海外企業を買収されたご経験がある方ならば、買収対象の経営陣がクロージング時にこれほどまでに多額の賞与を受け取るのか、と驚かれた方もいるでしょう。しかし、日本企業が売り手の場合、トランザクション・ボーナスの導入や支払いに、強い抵抗感を示されるケースが多いです。今回はトランザクション・ボーナスの功罪について山崎洋一(当社クロスボーダー&スペシャル・ソリューションズチーム共同ヘッド)が解説します。
ー トランザクション・ボーナスとは何ですか?
事業売却が成約(クローズ)することを条件に、売却対象事業の経営陣(「対象経営陣」)に払われる特別ボーナスです。逆に言えば、案件がクローズしない場合は支払いは発生しません。支払い主体は売り手(親会社)ではなく、売却対象の子会社であることが多いですが、その場合でも実質的な有利子負債とみなし、売却価格から差し引くため、売り手が経済的に負担することとなります。
金額はケースバイケースでかなり幅はありますが、トップ層では基本給の6~12か月分、或いはそれ以上に設定されることもあります。下の層になると数か月から6か月程度が相場です。要は対象経営陣の目の色が変わるくらいの水準です。付与対象の人数については、売却事業の規模やプロジェクト体制によりますが、数名から多いケースで10名超となることもあります。
ー そうすると、総額では億円単位にのぼることもあり得ますね。目的は何でしょうか?そこまで多額の金銭的負担を、売り手が負うメリットはあるのでしょうか?
ひとえに対象経営陣のモチベーションを上げることです。事業売却の準備に取り掛かる際、まずは対象経営陣に、「あなたはノンコアだ。これから売却する」と(言い方はともかく)伝えなければなりません。そう言われて「よし、今まで以上に頑張ろう」と思いますか?しかも、事業売却となると、日常業務も続けながら、マネージメント・プレゼンテーション(マネプレ)の準備や練習、デュー・ディリジェンス(DD)対応など、対象経営陣の業務量は控えめに見積もっても1.5倍にはなります。そして、一度でもM&Aをご経験された方ならご存知の通り、案件の成立には、対象経営陣に時間的にも気持ちの面でも案件に十二分にコミットしてもらうことが不可欠です。
他方、事業売却に際して売り手と経営陣の間で利益相反が生じることは珍しくありません。対象経営陣は、そもそも売却が成立しないことを望むかもしれません。故に、マネプレやDDにおいて、買い手候補に対し、経営陣が露骨に後ろ向きなトーンで話をしてしまうことが実際あります。特に、海外子会社の場合、日本本社とは物理的にも心理的にも距離があるせいか、このような場面に出くわすことが多いです。
ー 実際どの程度普及しているのでしょうか?
正確な統計ではありませんが、現場の肌感覚としては、欧米企業が事業や子会社を売却する場合は8-9割は導入している印象です。なお、売り手がプライベート・エクイティの場合は、トランザクション・ボーナス以前に、対象経営陣に株やストック・オプションが付与され、うまく(高く)売るインセンティブが投資実行時から導入されていることが多いです。
日本企業が売り手の場合ですが、過去に事業売却を経験された(そして、苦労された)企業が海外事業を売却されるケース、そして弊社がアドバイスさせていただく案件では、少なく見積もってもトランザクション・ボーナスの導入は過半を優に超えます。金額的にも先述した海外と同水準を支払うケースが多いです。他方、国内事業の売却の場合は、議論の遡上に上ることは徐々に増えてきましたが、まだ導入実績はゼロではないでしょうか(売り手がプライベート・エクイティの場合は除く)。
ー 日本企業の間で、なかなか普及しない理由はなんでしょうか?
まず、馴染み・前例がないこと。また、設計次第では相当な金額になります。それを、これからも自社に貢献して欲しい人材ではなく、数か月後に袂を分かつ人材に支払うことへの抵抗感も挙げられます。更には、売却対象事業の全従業員に付与する訳ではありません。売却対象事業のトップ層とDDなどに対応するプロジェクト・メンバーに限られます。つまり、売却対象事業の中にも、もらえる人ともらえない人の線引きが必要となります。この不公平感・不平等感も大きな理由の一つとなっています。
設計・水準次第では、売り手の経営層よりも高い報酬額になってしまいます。難しい判断であることは想像に難くありません。しかし、私が売り手アドバイザーを務める際は漏れなくトランザクション・ボーナスの導入を強くお勧めしています。それだけのメリットがあるからです。仮に同じ事業内容・同じ財務数値であっても、片方は何となく仕事を流している対象経営陣、もう片方は(金銭的な動機があるとはいえ)案件を成立させるべく、高い熱量をもって戦略を語り、事業を語る対象経営陣。どちらの会社が、より高く、より確実に売れるでしょうか。
ー トランザクション・ボーナス以外で、経営陣を動機づける術はないのでしょうか?
これもトランザクション・ボーナス導入とセットで、私がいつもお勧めしていることですが、コミュニケーションです。優秀な人ほど、お金だけでは動きません。単に、ボーナスの契約書をメールで送るだけでは不十分であり、売り手の然るべき方から、「新しいオーナーの下、更に成長して欲しい。これまで我が社に貢献してくれてありがとう」と直接、対象経営陣に伝えることです。こうしたコミュニケーションのためだけに、売り手の経営トップがわざわざ遠い海外の地まで赴くケースもありました。対象経営陣も意気に感じてモチベーションを高めることができたのではないでしょうか。
ー 具体的な設計にあたって金額以外で留意点はありますか?
一部を売却価格とリンクさせたり(高く売れると、金額が増える)、DD完了時や買い手候補からの入札書受領時など、案件の途中で支払う等、様々なバリエーションが存在します。その中で、冒頭述べたように、少なくとも総額の大部分は、売却の成立=クロージングを支払い条件とすることが最も重要と考えます。特に案件の後半になり、買い手=新しいオーナー/新しい上司、の顔が見えてくると、どうしても人間そちらの方に気持ちがなびき、売り手ではなく買い手の言うことを聞きたくなります。そのような状況では、必ず売却条件が悪くなります。
案件の前後半に関わらずですが、売り手と対象経営陣の間には、利益相反が生じやすいことは前述のとおりです。例えば、マネプレで開示する事業計画ですが、売却後、新しいオーナーの下での対象経営陣の業績連動賞与の目標値・基準値になることが多いです。つまり対象経営陣としては、これを低く見せることが将来の賞与増大、更には雇用維持につながる、他方で事業計画を下げてしまうと、売却価格が下がり、最悪の場合そもそも売れなくなってしまうという構造が、どのM&Aでも存在するのです。トランザクション・ボーナスは「残業代」ではありません。売り手と対象経営陣に、”売却成立”という一つの共通の利害を設定することで、利益相反を緩和し、より好条件での売却を実現するための「投資」なのです。
記事監修
この記事を監修している弊社担当者です。